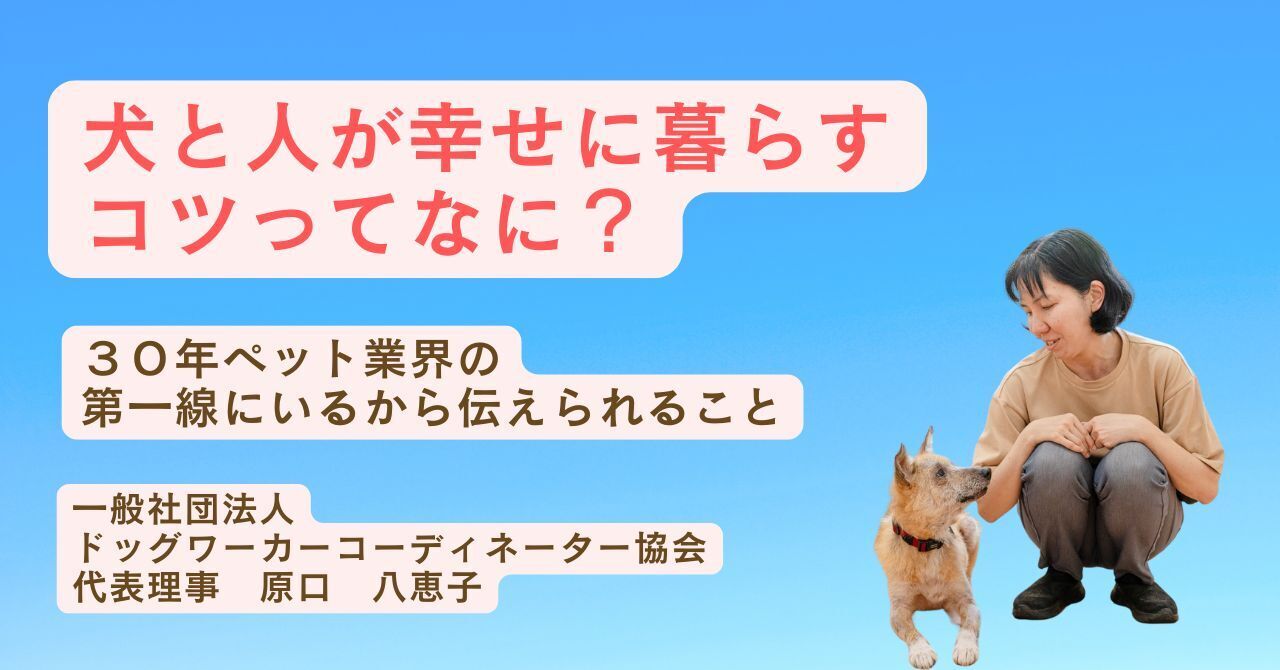
犬の食が細くなるのはなぜ?
2025年07月31日 18:18
 犬の「食が細い」には理由があります
犬の「食が細い」には理由があります
こんにちは。
ペット業界歴30年、ドッグトレーナーでありトリマーでもある私ハラグチが、
飼い主さんとワンちゃんが毎日を楽しく、心地よく過ごせるヒントをお届けしています。
今回は
「ワンちゃんの食が細くなる理由」
についてお話しします。
「食が細い」と何が困るの?
サロンにいらっしゃる飼い主さんから
「ご飯をよく残すんです」
「あまり食べないんですよ」
というご相談をよくいただきます。
その中でよく見られるのが、
全体的に食に対する意欲が弱いタイプのワンちゃんです。
実はこの「食が細い」という状態、
体調の異変に気づきにくいというデメリットがあります。
例えば私の家では、代々シュナウザーを飼っています。
シュナウザーはもともと食欲旺盛な犬種で、普段はバクバク食べます。
そんな子が急にご飯を食べなくなったら
「おかしいな?」とすぐ気づけるんですね。
でも、普段から食が細いワンちゃんだと、
具合が悪いのか、ただの気まぐれなのか判断がつきにくく、
異変のサインを見逃しやすくなります。
犬は本能的に、
体調不良を隠す生き物です。
なぜなら、野生の世界では弱みを見せると
外敵に狙われやすくなるからです。
また、群れの中でも「足手まとい」と判断され、
仲間はずれにされてしまうことがあるため、
本能的に“隠す”ようにできています。
さらに言葉が通じない以上、
「お腹が痛いよ」と訴えることはできません。
だからこそ、
飼い主さんが食欲の変化に早く気づけることがとても大切なんです。
食欲が落ちる理由と飼い主さんの対応パターン
多くの飼い主さんは、子犬の時期にワンちゃんを迎えられると思います。
その頃は成長期なので、何もしなくてもお腹が空いて
3食しっかり食べてくれることが多いです。
そのイメージがあるので、成犬になってから食べなくなると
「どうしてだろう?」と不安になる方も多いようです。
でも、大人になると体型も落ち着いて
それほどカロリーを必要としなくなります。
運動量や生活環境によっても違いますが、
子犬時代のような食欲が落ち着いてくるのは自然なことなんです。
ただ、ここで注意したいのは
飼い主さんの「心配しすぎ」が食欲低下に拍車をかけるケースです。
代表的なパターンを2つご紹介します。
① 構ってもらえるから食べない
食べないからといって、
ご飯を1粒ずつ口元に運んだり、声をかけたりしていませんか?
それがかえって「構ってもらえるご褒美」になってしまい、
食べないことで注目されるという学習につながってしまいます。
② 食べなければおいしいものが出てくる
「このフードは食べないから」と
鶏肉やチーズなどをトッピングしていませんか?
それが続くと
「食べなければもっとおいしいものがもらえる」
と覚えてしまい、どんどん偏食になっていきます。
また、日頃の運動量が少なかったり、
お留守番が長くて刺激がない生活が続くと、
自然と食欲も落ちてしまいます。
ついやりがちな「ご飯の置きっぱなし」
よく見かけるのが、
「後でお腹がすいたら食べるだろう」と
ご飯を長時間置いておくスタイルです。
でもそれはNG。
ドライフードでも風味が飛んでしまいますし、
湿気や酸化によってますます食べなくなります。
私自身、初代のワンちゃんにはそうしていた時期がありました。
でも、2頭目のシュナウザーを迎えたことで、
「食べないと取られちゃう!」という意識が働き、
ご飯をしっかり食べるようになったという経験があります。
「食べない子」にはこの方法がおすすめ!
ご飯を出したら、10分間だけ置いておく。
それで食べなかったら、潔く下げます。
そして次の食事(たとえば夕ご飯)まで、
間食やおやつは一切与えません。
これを繰り返すことで、
「今食べないと、食べられない」と学習し、
徐々に食べるようになります。
ずっと何かを口にしていると、
お腹が空かない=食欲がわかない
という状態が続いてしまいます。
しっかり時間を空けて「空腹をつくる」ことが大切です。
もちろん、体調に問題がある場合もあるので、
極端に痩せてきたり、元気がないときは獣医さんに相談してくださいね。
ちなみに、「うちの子ご飯食べないんです」と相談されるワンちゃんの中で、
実は太り気味な子が多いというのも現場でよくある話です。
ご飯は食べなくても、おやつやトッピングでカロリーを取っていて、
知らず知らずのうちに太ってしまっているんですね。
適正体重を保つことは、健康寿命を延ばすためにもとても大切です。
次回予告
次回は
「おやつの役割と食への意欲の育て方」
についてお話しします。
おやつはただのご褒美ではなく、
トレーニングやストレス軽減、ハズバンダリートレーニング(お手入れに慣らす練習)など
多くの場面で大切な役割を果たしています。
楽しみにしていてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。