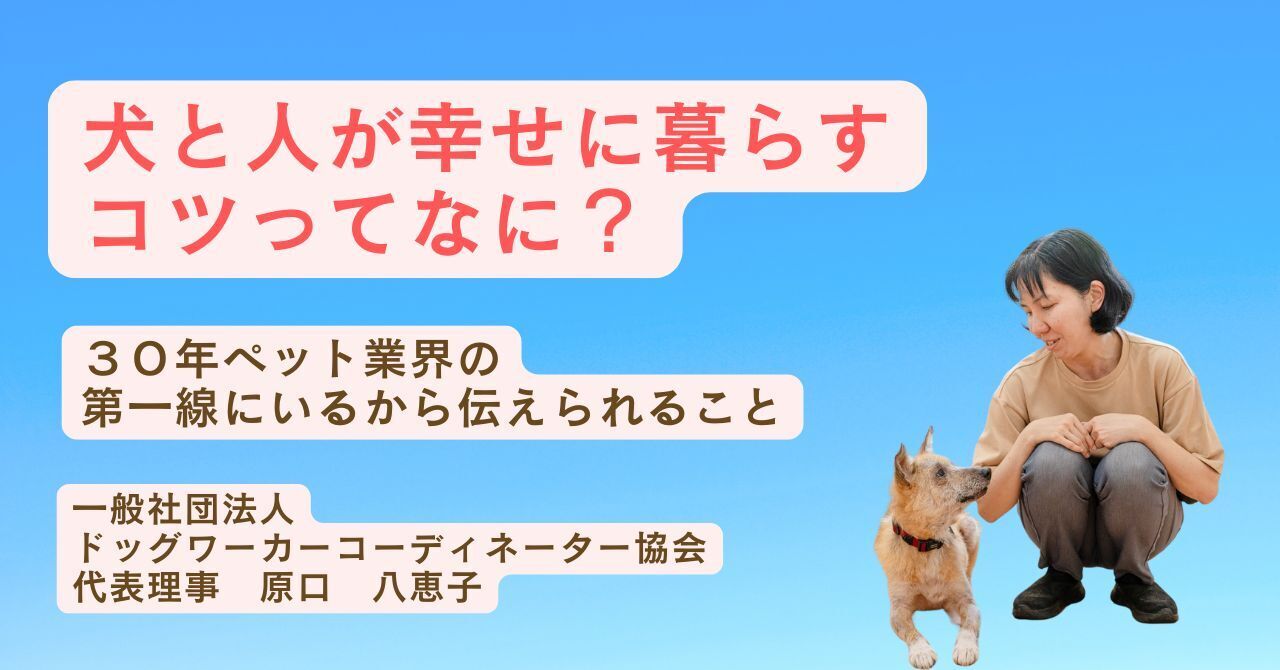
犬のしつけ!その無視の仕方に効果はあり?
2025年07月23日 17:37
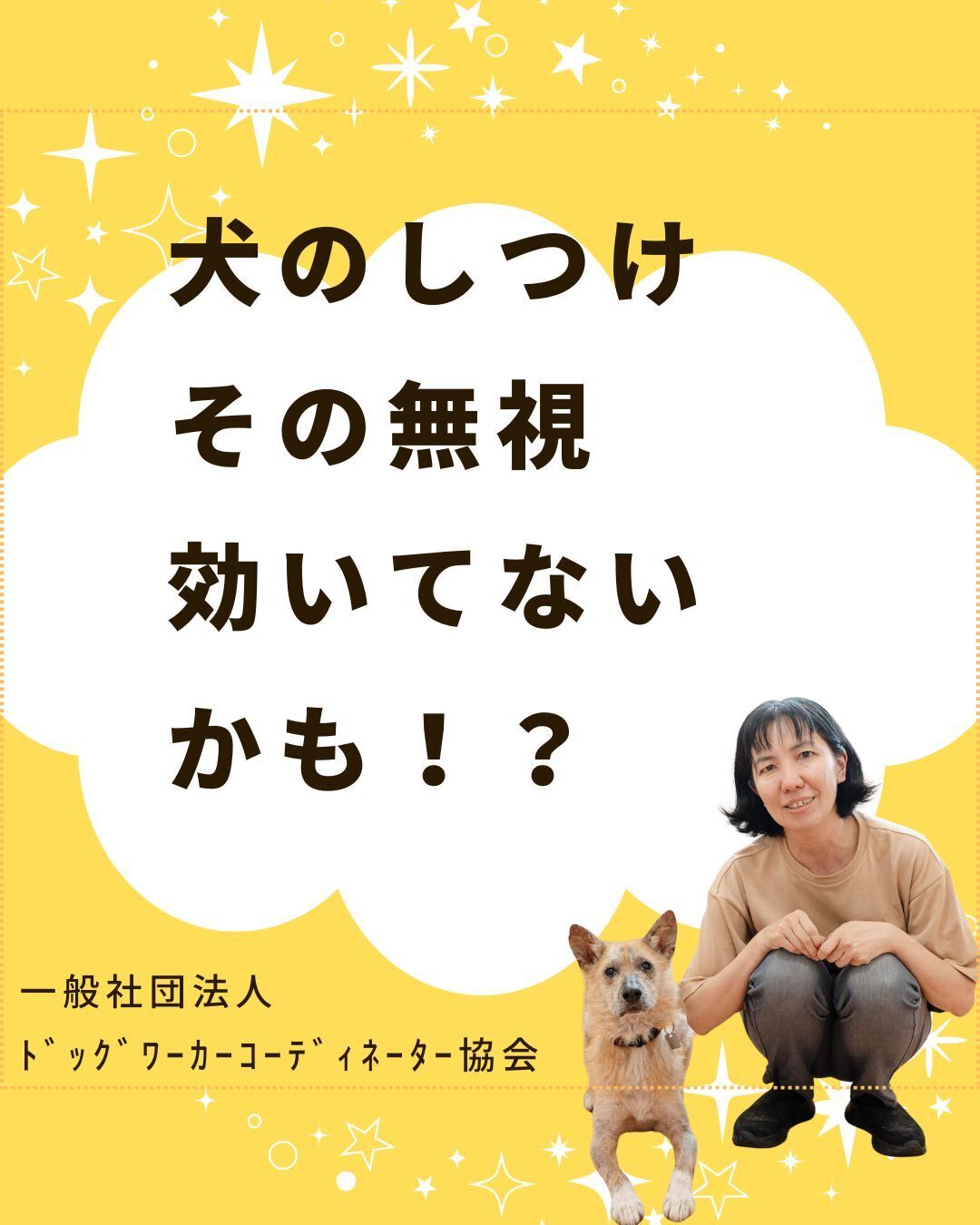 前回は、「しつけにとって有効な“無視”には、関係性が大切ですよ」というお話をしました。
前回は、「しつけにとって有効な“無視”には、関係性が大切ですよ」というお話をしました。
今回はその続きとして、
「無視しているつもりでも、実は無視になっていないのでは?」
「無視を続ける“人の忍耐力”が足りていないのでは?」
というテーマでお話しします。
ワンちゃんは、圧倒的に“暇”なんです。
日常の中で、何か楽しみになることや張り合いを探しています。
そんな時、身近にいる“人”の反応は
簡単に得られる最高の報酬になります。
たとえば、
無視しているつもりでも、
ついチラッと見てしまったりしますよね。
でもそれだけで
「今、お母さんが見た!」
と、ワンちゃんはうれしくなってしまうんです。
その“チラ見”が報酬となり、
その直前の行動がどんどん強化されていきます。
たとえば、興奮して飛びついてきたとき。
人は驚いて思わず押し返してしまいますよね。
でもその“押し返し”すら、ワンちゃんにとっては楽しい遊びになってしまうのです。
なので、もっと飛びつこう!となってしまいます。
「無視したつもり」でも、
実は“無視になっていない”ことがとても多いのです。
誰が対応するかによって行動が変わる場合、
ある人は正しく無視できていて、
ある人は“つもり”だけで報酬を与えてしまっている。
そうなると、当然効果に差が出てしまいます。
ワンちゃんは、0コンマ何秒の世界で生きています。
もし野生なら、一瞬の判断ミスで命を落とすこともあるからです。
そのため、人間のスピード感とはまったく違います。
さらに、犬はボディランゲージ(体の動きや表情)で対話する生き物です。
人のちょっとした動きや表情も、敏感に見ています。
たとえば、お母さんが頭に手をやっただけで
「この後はあれだな!」と予測して、ソワソワすることもあります。
つまり、飼い主の何気ないクセや習慣を、犬はすぐ覚えてしまうのです。
私も、トレーニングのときにおやつポーチをつけています。
「ヨシ」は報酬や解除の合図として使いますが、
その「ヨシ」を言う前に、つい手がポーチに伸びてしまうことがあります。
そうすると犬は、「ヨシ」よりも「ポーチに手をかけた」が合図だと覚えてしまい、
先に動き始めてしまうんですね。
こうした“人のクセ”にも犬は敏感に反応します。
だからこそ必要なのが、
人側の「忍耐力」です。
犬のトレーニングをしているようで、
実は「私の精神力が鍛えられてるなぁ」と感じることもよくあります。
では、どうやって“無視”を徹底していくのか?
たとえば、落ち着きのない子犬が
ぴょんぴょん跳ねているとします。
多くの飼い主さんは「落ち着きがなくて何もできない」と感じてしまいますが、
私はこういった子に対して、ぴょんぴょんしている間は一切の動きを止めます。
そして、跳びかかってきたときには無言で後ろに下がる。
そうすると、前足が自然に地面につきます。
そのタイミングで次のアクションに移ります。
オスワリをさせたり、できたら「ヨシ」でおやつをあげたりします。
またぴょんと跳ねたら、また無言でスッと引きます。
ここで大事なのは、「無言」です。
「また動いた!」などと声をかけてしまうと、
それがまた報酬になってしまいます。
なので、反応せず、静かに、淡々と対応します。
そして、四つ足がついた瞬間や、オスワリできた瞬間を逃さずに
「ヨシ」で報酬を与えます。
この
“無視”と“報酬”の繰り返し
が、効果を出すカギです。
個体差はありますが、
たいていの子は15分ほどで落ち着きが出てきます。
私はよく「犬もバカじゃない」と言うのですが、
ワンちゃんは意味のないことをずっと続けたりはしません。
「これ、やっても意味ないな」と気づいたとき、
自然と行動は変わっていくのです。
ゼロにはならなくても、改善はできます。
私が運営しているナーサリー(保育園)に通っている子の飼い主さんから
「おうちでオスワリするようになったんです」
「目を合わせてくれるようになったんです」
と喜びの声をいただくことがよくあります。
人との接し方が変わることで、
ワンちゃんの行動もどんどん変わっていくのです。
「無視」といっても、
その裏にはとても細やかな要素がたくさん含まれています。
困ったときには、ネットの情報に頼るのも一つですが、
モチベーショントレーニング(やる気を引き出す方法)を得意とする
プロのドッグトレーナーに相談するのが一番の近道です。
「落ち着かせたい」なら、
経験のあるトレーナーであれば、15分ほどで対応できることが多いですよ。
自分であれこれ悩まずに、
気軽にプロに頼ってみてくださいね。
次回は、「ご飯を食べなくなるのはなぜ?」というテーマでお届けします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。